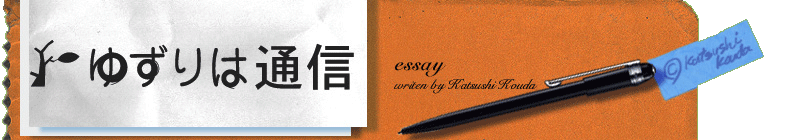富山駅前マル―ト4階の「くまざわ書店」で初めて本を買った。郊外店の「ブックスなかだ」を愛用しているが、駅での待ち合わせ、時間つぶしで利用していると、何か申し訳ない気持ちになりかけていた。人間心理の不思議さ。浮気をするような感じである。立ち読みでひょいと手にしたのが加藤陽子著「歴史の本棚」(毎日新聞出版)。22年の刊行だが、1760円なのがよかったようだが、本の並べ方が絶妙だった。書店員のレベルの高さでもある。店名からしてローカルなので、JR関連書店かと思っていたが、何と東京・八王子本社で、日本で3番目の規模だという。書店撤退の中で、見えない工夫をしているのだろう。
加藤陽子が読んできた歴史学の書評が、いいリズムで綴られている。心地よく、ページが進む。毎日新聞出版の峰晴子・編集者への信頼感もあふれている。カバー写真は加藤の書斎だが、同僚の高橋勝視が撮っている。「高橋君、撮ってよ」。そんな職場の声が聞こえてきそうだ。みすず書房の「読書アンケート2024」が薄っぺらに見えてくる。
1930年代の日本の軍事と外交を専門とする加藤だが、研究者魂の一端を知ることができた。1か所でも詰め切れない事項があり、「あの本に出ていたはずだ」となれば全巻を読み直して当該箇所を探し出す。江戸中期の儒者・荻生徂徠はわずか2文字の出典を確定するため、「漢書」120巻を調べ直したとの逸話があるが、それに劣らない。
さりながら、「歴史とは何か」は究極「人間とは何か」である。読む前と後で、風景が違って見えてくるというが、柴田錬三郎から松本清張までひもとく。「一読を薦めたい」これが続く。加藤陽子ゼミに入ったら大変だが、面白いことは間違いない。
ところで既にご存じだろうが、著者の加藤陽子は2020年、日本学術会議メンバーの推薦をうけながら、任命されなかった6人のひとり。任命拒否理由を明らかにしないまま、政府は3月7日、日本学術会議を特殊法人化する法案を閣議決定した。「金を出す以上は好き勝手はさせない」という小役人レベルの発想を続けてきた結果である。
「歴史の本棚」の1冊に「帝国の計画とファシズム 革新官僚、満州国と戦時下日本国家」を挙げている。全面戦争を前に、経済力は国力の一要素に過ぎず、人間の労働力と精神力を最大限動員すれば、物資の量や資金力の差はどうにでもなる。そう説いて2000万人を死に追いやった。そのひとりは岸信介である。