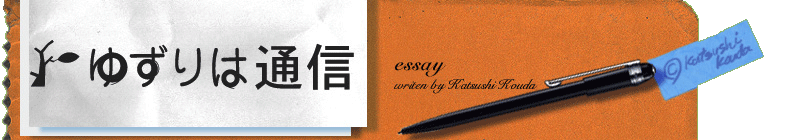ニューヨークタイムスは「トランプ再選はこの国と世界に危険をもたらす」と昨年から警鐘を鳴らし続けた。第1次政権では彼自身の準備不足や官僚機構の抵抗により最悪の事態は避けられたが、今度再選されたら、もう止めてくれる人たちは存在しない。しかし、タイムス紙の論調は完全に空回りし、米国民に届くことはなかった。
昨年末の日経コラムはこう綴っている。タイムス紙は電子版購読者が1000万人を超え、新聞業界が斜陽化する中でうらやむばかりの経営状況といっていい。ところが更に「進歩派」読者を得るために、記事が左傾化し過ぎたのではないか。エリートの「正しい議論」が「思い上がり」と見なされ、拒絶された。米国には進歩的なエリートが実際には存在しないのに、ひとり言をいう新聞になっている。
さて、日本でも失われた30年の大きな原因が、報道の自由度ランキング70位に沈むマスコミを挙げるのは波頭亮・戦略系コンサルタント。「日本の新構想」(小学館新書)で、鋭く指摘している。日本経済の不調は政策的選択によって必然的にもたらされた。成長に必要な資本投資が行われず、労働は少子高齢化に、働き方改革での労働時間抑制が加わり、多くの国よりも年間100時間少なくなった。テクノロジーや人材能力ではかる労働生産性はOECD38国中30位である。経済政策にいたっては、消費税を上げて、法人税を下げ、企業はその収益を賃金に回さず、投資もせず、配当に回していた。消費税と社会保険料を上げて国民の可処分所得を押さえてきたのだ。これを国民に正しく伝えてこなかった。アベノミクスなる欺瞞に満ちた政策に対する批判報道を怠ってきた責任は極めて重い。
波頭の持論だが、資本主義という苛烈な競争を闘いつつ、同時に福祉国家的に国民を手厚く保護することは矛盾しない。成熟国家において非常に有効な国家運営の方法論である。
トランプ関税騒動で考えるべきは、こうした構造転換の好機だということ。大きく動かすことである。現金給付案などもってのほかである。あるべく国家構想をこんな時こそ、議論すべきである。