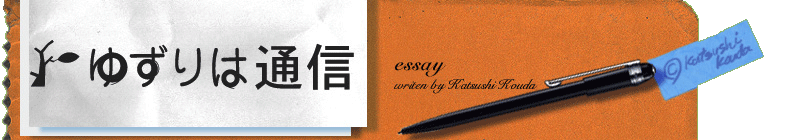80年も生きて、「自分が何者なのか」「どうしてそんな思考をするのか」、時にそんな問いに揺さぶられる。遺伝子に由来するものか、後天的なものか。ひょっとして多重人格なのではないか。
みすず書房のWEBみすず4月号の「トラウマ・解離・安克昌」を読み出して、つい読み切ってしまった。精神科医の松本俊彦が綴っている。解離というのは解離性同一性障害(DID)で多重人格のこと。臨床の現場からの報告は切迫感があり、精神科医の難しさ、求められるレベルの高さに慄然とさせられた。
引用したい。交代人格が出現した場合には、まずはきちんと自己紹介して、その凶暴な人格の怒りの背後にある悲しみを見いだすように努める。ひとわたり交代人格の主張に耳を傾けたら、登場と発言をねぎらった上で、最後は主人格に戻ってもらう。交代人格のまま帰すと、病院からの帰路でいろいろとトラブルを起こす危険がある。交代人格が出現していない場合でも、決して交代人格を批判してはならない。主人格の背後で交代人格は医師とのやりとりを聴いている可能性が高い。いかに粗暴で、一見邪悪な考えを持っている交代人格であっても、すべて意味があって存在している。凶暴な人格は患者が暴力から自分の身を守るのに役立ってきただろうし、性的に奔放で誘惑的な人格も、暴力的に組み敷かれるのを回避し、状況を自分のコントロール下に治めるのに役立った可能性がある。
主人格と交代人格、自分ともう一人の自分。精神科医はどちらにも語りかける。統合失調症は慢性化してしまうと人格が荒廃してもう治らない。そんな諦観にノーを突きつけたのは中井久夫である。慢性状態も不断に変化し続ける寛解の過程にほかならない。患者と医師が希望を共有できるかどうかが、治療において非常に大きな意味を持っている。精神医療の現状がどうなっているのか。そんな手掛かりの一端も見せてもらった。
ことの発端は阪神淡路大震災で、神戸大学医学部精神科の中井久夫が中心となって被災者に寄り添う「こころのケア」の取り組みが行われていた。いうまでもなく中井久夫は「こころの医師」の代名詞となっており、その中井を師と仰ぐ在日3世の安克昌は現場の中心となり、著者の松本も横浜市立大学から駆け付けていた。そこから、新たな精神医学上のムーブメントが起こった。
キーワードが「トラウマ・解離・安克昌」。我流の解釈だが、トラウマが解離現象を引き起こし、安克昌の心のケアが寛解をもたらした。統合失調症の精神病理で名を馳せた中井だが、その中井を安が変節させたという。
安がその間を記録したのが「心の傷を癒すということ」。テレビドラマにもなっている。その安だが、2000年に肝細胞癌で亡くなっている。39歳で、3児が生まれた2日後であった。
アフリカを出て、さまよいつつ、命をつないできた私であり、あなた。縄文時代にも、弥生時代にも分裂病は存在していた。正常も異常もないのだ。すべてを受け入れて、生きていくしかないのだ。