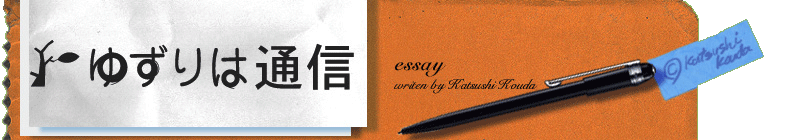1月19日、来期の町内会長を決める会合があった。わが町内は班長の互選で会長を決め、1年で交代する。191戸の全世帯が加入し、13班の構成。40年余の歴史があり、かなり大きな町内だ。班長13名が全員参加して始まった。会長だけは絶対に受けないぞ、と悲壮感さえ漂う。どういうわけか奥さんの参加が多い。女性の町内会長はまずないだろうと踏んでいる。男性参加をよく見ると、ほぼ鰥夫(やもめ)である。まずはそれぞれ自己紹介しながら、なぜ会長ができないかを述べていく。「八十路を迎える爺さんである上に、20年前に会長をやっており、今回はお許し願いたい」が私の弁。一巡したところで、何となく最近奥さんを亡くした60代の男性が候補に目されそうな雰囲気に。町内の付き合いは家内に任せきりで全くわからないうえに、日常の切り回しも覚束ない状況で、その上に会長の重責を抱えるのは自信が無い。声にも張りがない。無理強いはできない空気になった。しばらく、重い空気が支配する。こんな空気に弱い。最年長の私が助け船を出すしかない。私が会長、彼が会長補佐を兼ねた役職でどうだろう。そんな提案に拍手が湧く。やむを得ない。
少子高齢化は町内会でも急激に進み、空き家、独居世帯が目に見えて増えている。子ども声が全く聞こえてこない。貧困、孤立、孤独、不安などでコミュニティを維持していく困難さが無限に広がっているようにみえる。さて、自ら呼び込んだ難局にどう立ち向かう。とにかく着眼大局、着手小局で、面白く実験する場を作り出していくしかない。
気分転換の本屋巡りだが、最近は単行本が3000円台が当たり前のようになり、新書コーナーに眼がいく。出版不況を嘆きながら、行動は不況を加速させているようで心苦しい。それでも見つかった。「町内会―コミュニティからみる日本近代」(ちくま新書)で、著者は玉野和志。これに加えて2000年刊行の「ボランタリー経済学への招待」(実業の日本社・下河辺淳編集)、2009年の「コミュニティを問いなおす」(ちくま新書・広井良典著)。この3冊を机上に重ねた。4月スタートなので、この1か月が勝負となる。
例えば小型除雪機を富山市から借りているが、この保管、運転を3人のボランティアに委ねている。これに何とか手当を払いたい。除雪を依頼したい人は1シーズン3000円程度支払う。できれば地域通貨(といっても紙切れに印鑑)システムにしたい。この方式で老人独居に対して弁当、買い物代行などサービス有料化などを目論む。
夢をみているのだが、はてさて、どうなるものやら。