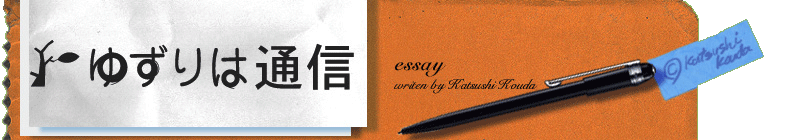気休めだが、夕方6時10分になるとNHK第2放送のスイッチを入れる。「まいにちハングル講座」。まったく頭に入らない。素通りしていくだけで、何も残らない。意地でしがみついている。5月号をぱらぱらとめくっていると巻末に、何と斎藤真理子が「私の好きな韓国文学」なるエッセーを綴っている。ご存じ韓国語翻訳者だが、実に幅広い活動をしていて、文芸評論の姉・斎藤美奈子ともども才女姉妹といっていい。きっとNHK出版から単行本で刊行されるのだろう。
さて、テキスト5月号で取り上げているのが、74年生まれのキム・スム(김숨)だ。大田(てじょん)大学の社会福祉学科を卒業しているが、97年には作家デビューをし、数々の文学賞を受賞している。とりわけ「さすらう地」を挙げたい。
1860年代、帝政ロシアは住む人のほとんどいない極東の沿海地域を入植地として開放し、極貧状態にあった朝鮮半島北部の農民たちを積極的に受け入れた。移住者たちは、祖国が日本の侵略に苦しめられ、1910年には日本に併合される一方で、ひっそりと繁栄を果たしていた。しかし1937年、ソビエトと日本の国境紛争が悪化すると、スターリンは朝鮮人が日本のスパイとなることを恐れて、彼らを極東からソ連内のカザフスタン、ウズベキスタンへと強制的に移住させ、そこで集団農場を営ませることを決めた。スターリンの苛烈さは、日本の侵略の更にうえを行く。幾万もの朝鮮人が、ある日突然、荷物をまとめるよう命じられ、窓のない家畜輸送列車に押し込められた。シベリアの厳しい冬に約6000キロを移動する旅は過酷なものだった。土地を追われた人々はやがて、約束された建材も現金の援助も、決してやってこないことを悟った。昔からずっと米を作って暮らしてきた農民たちにとっては、中央アジアの乾燥した土地や遊牧の文化に順応することも容易ではなかった。この民族の強さは、約500万人を超えるコリアンが世界に分散し生きていることだ。
「さすらう地」は、歴史の中で可視化されてこなかった人々の声を取りこぼすまいと綴る。「ママ、ぼくたちは〝るろうのたみ〟になるの」「ソビエト護衛隊は、私たちをチタに連れていって銃殺するんですって」。朝鮮で生きられず故郷を捨ててきた彼らにとって、土地を所有することは念願であった。土地への執着こそが自分たちを苦しめるのではないか。土地を追いかけてきたのに、土地そのものがさすらっている。
ノーベル賞を受賞したハン・ガンも、済州島4.3事件を「別れを告げない」で人々の声を綴っているように、韓国文学の奥深さと、脈々とつながる伝統を感じる。
斎藤真理子のエッセイを読むために、7月号テキストを買った。悪友は、もうハングルを勉強しなくてもAIが自動翻訳をやってくれる。時代はもう爺さんを相手にしていないのだ、と切り捨てる。