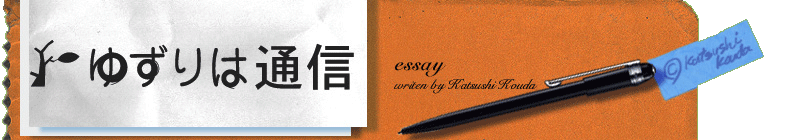中1の孫娘の読書感想文の課題図書だと聞いて挑戦してみた。2016年刊行の「君の膵臓をたべたい」。まったく知らない作家・住野よるのデビュー作。本屋大賞2位となり、販売部数は300万部を超えている。ジジも感想文を書けというので、約束せざるを得なかった。文庫で734円。版元が軟派な「週刊大衆」を出している双葉社。とにかく読んで、書かざるを得ない。
Man is mortal(人間は死ぬべき運命にある)。高校に入学して初めての英語の授業で、教師はこのフレーズを覚えておいてほしいといった。「君の膵臓・・」は、高校生の主人公・山内桜良の葬儀で始まるのだが、このフレーズがよみがえった。私は80歳である。いろいろな肉親の死を経験してきたのだが、つい忘れてしまっている。誰しもそうだ。つい忘れて、いつも明日があると思ってしまう。つまり、死を忘れてしまわないと生きられないのが人間なのだ。
余命1年の女子高校生が、死を意識して生きなければならない。つぶれそうな気持を、必死に支えていなくてはならない厳しさは想像を絶する。小説を書くというのは、こんな主人公を選んで書き進んでいく。小説家の必要な才能で、大事なポイント。
そして、そのことを家族以外で知るのは、同級生の志賀春樹のみ。「共病日記」と称する、遺書ともいえるメモがまっさらな文庫本に書き留められている。それを春樹は偶然拾って、見てしまった。誰にも話すな、という桜良。二人は秘密を共有しながら、急接近していく。触れてはならないものを避けながら、ふざけあう二人。ある時、桜良のカバンの中に入っている膵臓の薬品を見て、春樹が見てはならないものを見てしまったと驚く。
ところが、桜良は膵臓の調子が悪くなり、入院する。その寛解を得て家に帰る途上で、通り魔に刺殺されてしまうという結末だ。生老病死以外に、事故死など予期せぬことで命が絶たれることもある。人生はいつもあっけなく、中途半端で終わっていくということ。あわれ、ともいう。
もうひとつのストーリーが、桜良の親友で同級生の滝本恭子。彼女は桜良の病気のことは知らない。いや、知らせてもらっていない。事件後、春樹に喫茶店で共病日記を渡され、それを読み、人目憚(ひとめはばか)らず号泣する。桜良の遺言ともいうべき願いは、春樹と恭子が仲良くなること。桜良は、恭子に自分の分まで生きてほしい、と願った。ふたりは桜良の墓参りをし、山内家にも出かける。桜良の願い通りに生きることがせめてもの供養であると思っている。そんな人生があってもいいのでは、といっている。
はてさて、この小説を書いた住野よるは女性だろうと思っていたが、意外にも大阪在住の男性で、初めての作品だという。80歳の読者からすれば、桜良の母親が共病日記を春樹に渡したシーン。春樹の母親が桜良の家を訪ねると知り、さりげなく1万円を香典にしなさいと渡すシーン。このふたつが心に残った。
しかし、住野の次の作品を読むことはないと思う。