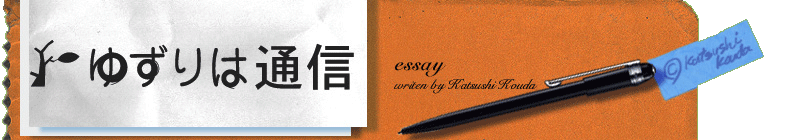1964年春、東京での下宿生活が始まった。新宿区柏木の淀橋青果市場に近い森山多美方の4畳半。共同トイレで、小さな台所が付いていた。それでも大学生協で机と本棚を揃えた。受験勉強から解放されて、本当の勉強を始めようと思っていた。わからないまま月刊文藝春秋と月刊中央公論を取り敢えず買い揃えた。もちろん辞書「広辞苑」がブックスタンド代わりに立てていた。何となくこれから始まる学生生活の希望みたいなものを感じた記憶がある。夏休みもすぐには帰省せず、大学図書館に通うことにした。そこの雑誌コーナーに並んでいたのが月刊「世界」で、ちょっと違うなと思った。難解な活字が並び、レベルが違うという印象だった。何となく、これを読みこなさなければと思わせた。以来60年余、購読を続けている。
1000号のうち700号は手にしていることになる。思えば、羅針盤といっていい存在であった。その部数だが公称で追ってみると、1992年12万部、95年から05年まで8万部、04年から12年まで7万部、13年から20年までは6万部、21年以降は4万部と漸減している。恐らく現在はもっと厳しい部数になっていることは間違いない。部数が落ちても、編集に賭ける努力は変わらない。世界の編集長は、吉野源三郎に始まり、安江良介、山口昭男、岡本厚、清宮美雅子、熊谷伸一郎、堀由貴子と続く。岩波の土性骨であることは変わらない。
一方で岩波新書も、憧れの本であった。大学の恩師宅玄関脇の書棚に、全巻揃って収められていた。恩師曰く、岩波新書を書くのが夢だ。ざっと10万部は確実に売れて、印税だけで百万単位で入る。学会に出ても、リスペクトされるので誇らしいといっていた。
かくいう小生も、岩波書店と聞くと、センチメンタルジャーニーになってしまう。実は入社試験も体験させてもらった。教授推薦不要の一般公募なので、誰でも受けることができた。ざっと2000人が受験し、数人が入るという天文学的な難関出版社だった。初任給も世間相場の2倍で、新入社員は岩波のPR誌「図書」の送付が仕事だと聞かされた。社会人になって、東京出張の折に神田神保町にある岩波書店専門の信山社に立ち寄るのが楽しみだったし、時間があれば岩波ホールにも顔を出した。高野悦子支配人は魚津高等女学校出身である。映画「芙蓉鎮」が忘れ難い。
栄枯盛衰は世の習いというが、岩波書店の凋落は眼を覆うばかりだ。神田神保町にその面影はない。岩波だけに限らず、出版界はコミックを持っていない新潮社、文藝春秋などは苦戦を強いられている。書店も苦しい。愛用していた大型書店が次々と閉店していて、時間がつぶせない。